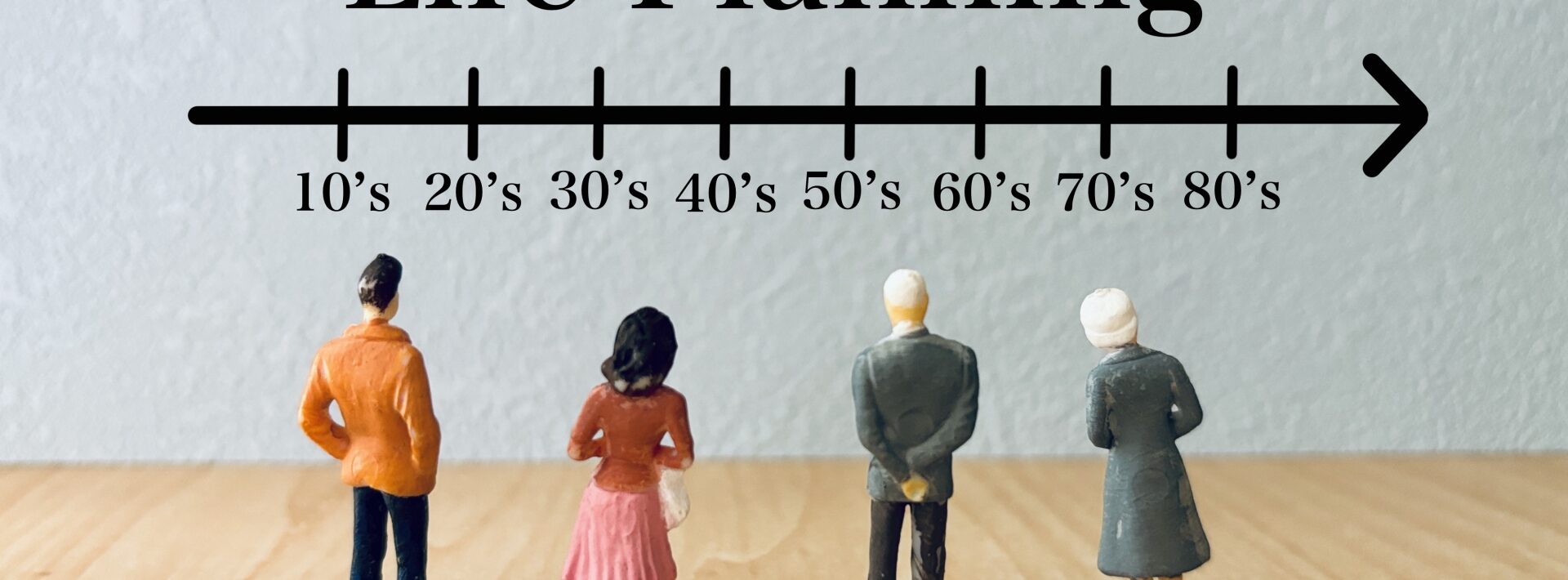”治療と仕事の両立支援”とは、病気を抱えながらも、働く意欲や能力のある従業員が、仕事を理由として治療の機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由に職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながらワークライフバランスを実現し、安心して生き生きと働き続けられることを言います。
現在、労働者の約4割が何らかの疾病を抱ながら働いており、特に2人に1人は「がん」に罹患し、うち3人に1人は働く世代(20~64歳)と言われています。
がん患者を対象に調査を行ったところ、診断後に3割ほどが依願退職・解雇されているというデータも…。
一方、近年の治療技術の進歩により「がん」の5年生存率は6割近くとなり、長く付き合う病気へと変化しています。さらに、早期発見であれば治癒が見込まれ、早期に職場復帰することができます。
仮にもし、必要な選択肢や制度、配慮の方法を知らなかったために、仕事を辞めなければならないとしたら、それは企業にとっても大切な「人財」を失うことになります。
がん患者等の就労支援を行うということは、本人だけの問題ではなく、そのご家族、雇っている企業…さらには貢献している社会全体の問題であると考えます。
また、社会での活動から利益を得ている企業にとっては社会的責任とも言え、その支援が我々専門家の役割でもあります。
”治療と仕事の両立支援”の取り組みは、「働き方改革」の重要な柱となっており、健康経営優良法人の認定基準にも含まれ、その実践は超高齢化と生産年齢人口の減少が進む我が国において、企業イメージの向上や人材の発掘・確保・定着等につながります。
しかし、実際に“治療と仕事の両立支援”を進めていくにあたり、「具体的に何をすればよいのか?」「現状何ができていないのか?」「何から始めればよいのか?」など、疑問を感じている事業主様等も多いのではないでしょうか。
一般的に職場・患者本人・医療者が情報を的確に共有する必要があると言われますが、私が社労士として現場で強く感じるのは、本人だけでなく一緒に働いてる同僚等への配慮はとてもとても大切であるということ。
すなわちそれは、組織全体の課題として捉える必要があります。
杉本社会保険労務士事務所は、2010年から多くのがん患者さん・事業主様の相談に乗ってまいりました。
両立支援には、患者さんや医療者だけでなく、雇っている企業側・そこで働いている方抜きには成り立ちません。
とは言え、企業側も従業員から「がん」告知をされたとしても、どう対応していけばいいのか、どう接すればいいのかわからないのが本音ではないでしょうか…。
「多様な働き方」「働きやすい職場環境づくり」という考えのもと、当事務所では事業主様を対象に問題解決のお手伝いをしております。
なぜ両立支援なのか
| 事業主の責務 | 社会的責任 | 社会的要請 |
|---|---|---|
| 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(略称労働政策総合推進法)に、治療と仕事の両立支援に対する事業主の責務(努力義務)が明記されました。 なお、施行期日は令和8年4月1日です。 | 治療と仕事の両立支援は、働き方改革の柱でもあり、企業に求められる社会的責任の一つです。多様な人材を活用し、社会的に価値ある事業を展開することで、企業の信頼性や評価を高めることができ、さらに企業のブランド力や競争力の向上にも寄与します。 | 労働人口の減少・高齢化、医療の進歩に伴い、病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者への サポートが求められています。 がんをはじめとする継続して治療が必要となった人材が、治療と仕事を両立できるよう支援することは社会全体にとって重要なことです。 |
企業にとっての課題と効果
がんなどの病気によって従業員が退職するということは、従業員が培った経験・ノウハウを失うことになり、企業にとっては大きな損失です。
「治療と仕事の両立」を支援することは、優秀な人材の確保、生産性の向上につながることが期待されます。
さらに、病気を抱える従業員が働きやすい職場は、育児や介護その他の様々な事情を抱える従業員にとっても働きやすい職場であるとも言えます。
一方、従業員(患者)や家族にとって、働くことは生活費や治療費のためであると同時に、“アイデンティティ・生きがい”でもあります。
「治療と仕事の両立・がん患者等の就労支援」を実現することで、従業員満足度の向上や働きがいの創出、新たな人材の発掘・確保・定着、さらには企業イメージの向上や社会的認知度の高まりなどの波及的な効果も期待できます。
特に昨今、少子高齢化が進む中、新規採用もままならないほどの人材不足に悩む会社では、既存社員の高齢化も心配されるところです。高齢になってくると、疾病リスクが高くなるのは当然です。そのため、疾病を抱え治療をしながら働く労働者が今後ますます増えてくることを見据え、治療と仕事の両立ができる職場づくりを行うことが大切になってきます。
法的背景だけではなく、「安心して自社で働き続けられる職場を目指す」といった事業主様・経営層のメッセージを示した上で、継続的な人材確保・定着や従業員のモチベーション向上、および多様な人材活用による組織や事業の活性化などに両立支援の必要性や意義があります。
就労・両立支援

社内制度整備・構築
両立支援を進めるには、規程も含め、社内の体制を整える必要があります。
休職前⇒休職中⇒復職⇒経過観察中と段階に応じて配慮できるよう、制度構築等お手伝いいたします。
また、従業員が安心して相談や申し出が出来る窓口の設置もお手伝いいたします。

社内研修・セミナー
治療と仕事の両立支援は「誰もが当事者になり得る」と捉えられるよう、全社員を対象に研修などを通じて理解を深めることが重要です。従業員から突然がん等、病気を告知されてもどう接し対応していいかわからない、具体的な事例・実際の対応等含め、お伝えいたします。
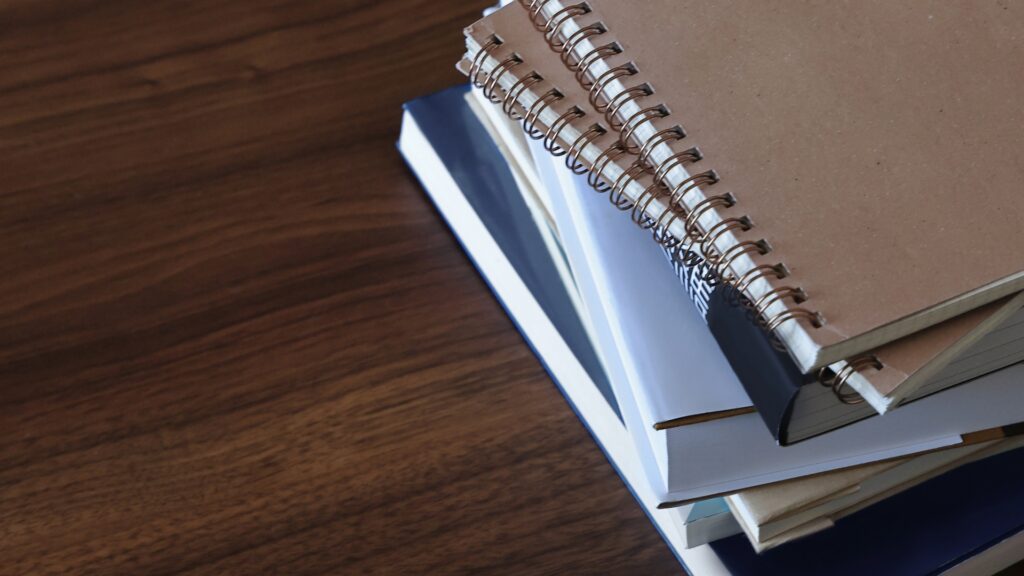
両立「休職・復職」支援
病気によっては治療の経過が異なり、それぞれの治療方針にあった働き方・配慮が必要になります。
従業員・医療者も含めた支援体制が整えられるようサポートいたします。
また、相談申し出後の個人情報等の扱いから就業措置・配慮の決定に至るまでサポートいたします。
専門家が支援します!
| 社会保険労務士 | 社会福祉士 | 両立支援コーディネーター |
| 社労士法に基づいた国家資格者。 企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働保険等に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っており、治療と仕事の両立支援に必要な社内制度や法的な面も含めた相談支援など、人事労務の専門家として、企業側・従業員側双方の視点を保ちながら問題解決の支援を行います。 | 社会福祉士は、同法に基づく名称独占の国家資格であり、ソーシャルワーカーとも呼ばれます。 社会福祉士は、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいいます。 | 治療と仕事の両立に向けて、支援対象者、主治医、会社などのコミュニケーションが円滑に行われるよう支援する者とされています。 支援対象者が治療と仕事を両立できるよう、それぞれの立場に応じた支援の実施及び両立支援に関わる関係者との調整を行うことがその役割として求められています。 独立行政法人「労働者健康安全機構」では研修事業を実施し、両立支援コーディネーターの養成を図っています。 |
|---|
料金体系
相談までは社会貢献活動として無料としていますが、制度構築、規程・書類等の作成、セミナー・研修、両立支援案策定等、具体的なご依頼に関しては顧問先様もしくは顧問契約を頂いたお客様に限定しております。